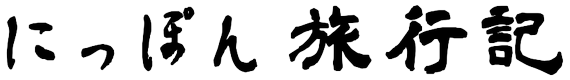上毛三山のひとつ榛名山へ行ってきました。
上毛三山とは群馬県を代表する赤城山、妙義山、榛名山の総称です。
上毛かるたが端的に表現しているので紹介します。
赤城山「裾野は長し赤城山」
妙義山「紅葉に映える妙義山」
榛名山「登る榛名のキャンプ村」
う~む…。榛名山だけ山のことを言っていないな。
他の二山のようにかっこよく〆れなかった感が…。キャンプ村が有名だったのっていつの時代か?って感じだし。
まぁ、そんなことはどーでもよいのです。
正直言って赤城山よりは榛名山の方が観光スポットに恵まれています。
湖&榛名富士は美しいし、うどん食べれるし(水沢うどん)、温泉入れるし(伊香保温泉)、榛名神社は立派だし…etc.
今回は榛名富士を中心の風景を見ていきましょう!
榛名富士と榛名湖

榛名山山頂にあるカルデラ湖と中央火口丘の榛名富士です。
カルデラは噴火でマグマなどが噴出した後の何もない空間に地表が落ち凹地(くぼち)になったもののことをいいます。
中央火口丘とはカルデラ内にできた小さな火山のことです。

榛名富士山頂までロープウェイで向かいます。
榛名高原駅の群馬県高崎市榛名湖町845−1です。

山頂に着きました。
探索してみましょう。

まず目に止まった祠。
このお社は榛名山の南面中腹に鎮座千四百余年の歴史を有する延喜式内の名社榛名神社の所轄する末社の一社です由緒は不詳ですがこの山が日本の最高峰駿河の富士山に非常によく似て居り榛名富士と呼ばれたことから浅間神社と同じ神様が祭られたと思われます富士山権現と銘ある御正体(お鏡)が榛名神社に保存せられて居ることからとても古いお社です頂上が本殿でここは遥拝所です
とのことです。
燃え盛る炎の中で出産した女神『木花咲耶姫 (このはなのさくやびめ)』が御祭神。
ちなみにその時産んだ息子の一人の孫が初代天皇『神武天皇』だそうです。

富士山神社鳥居。

富士山神社の本殿。紅白がなんだか眩しく感じます。
古くから縁結びお産の神様として近郷の信仰を集め、山開きを迎えると男女が長蛇の列をなして登山参拝しに来ていたそうです。縁結びと商売の神様は今も昔も大人気ですね!

本殿から少し下がった場所にある石碑四基。
左から饒速日命、保食大神、榛名富士大神、石長姫大神。
・饒速日命(にぎはやひのみこと)
天上から河内(大阪)に天下りしてきた神様。河内の豪族の長『長髄彦』の妹を娶りここを支配しました。神武天皇が日向から大和へ東征したとき長髄彦は両者神様だと理解するが神武天皇と闘い続け、饒速日命は長髄彦を殺害。その後饒速日命は神武天皇に従う。ちょっと意味が解らない…。なんで祀られているんだろう?
・保食大神(うけもちのかみ)
陸に向いて米を吐き、海に向いて魚を吐き、山に向いて獣を吐いて月読命(つくよみ)をもてなしましたが『口から吐いたものなんか喰えるか!』と怒られ殺されてしまった可哀想な神様。さらに御遺体から様々な食物が出てきてみんなびっくり!五穀豊穣の神様です。
・榛名富士大神
木花咲耶姫 (このはなのさくやびめ)のことです。
・石長姫大神(いわながひめ)
木花咲耶姫のお姉さんで姉妹揃ってニニギという神様に嫁ぎました。子孫たちが『木花咲耶姫は花のように栄えるよう』『石長姫は石のように永遠に生きられるよう』願いを込めて父の大山祇神(おおやまつみ)は送り出しましたが、しかしニニギは石長姫が醜いといい追い返します。このことにより恨み(呪い)を買い子孫たちは短命になってしまいましたとさ。これが人間が短命である所以です。(別に短命だと思わないですけどね)

さて下界へ戻ります。

湖畔に鎮座する御沼龗神社(みぬまおかみじんじゃ)、御祭神は高龗神(たかおかみのかみ)です。
旱が起きると雨乞いの神事をおこなうため各地から人々が集まってきたようです。
左側にある石碑は榛名山麓にある箕輪城が落城したとき無念のまま湖へ入水したお姫様のものだといわれています。

おしまい!