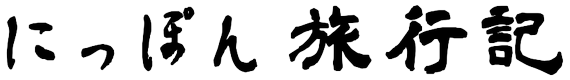二王座歴史の道は武家屋敷や寺院が立ち並ぶ臼杵の城下町です。
名の由来は二王座地区の祇園社(現八坂神社)に仁王門があったからとされています。
『におう』→『におうが座する』→『におざ』ということでしょうか。
それでは二王座歴史の道を紹介します。
二王座歴史の道の場所

東九州自動車道の臼杵ICを下りて右折します。しばらく直進して中須賀橋東の信号を右折すると臼杵城の案内板が出てきます。駐車場は城の近くにある市営下屋敷前駐車場が便利です。
臼杵城からそれ程離れていないので、↑の駐車場に停めて歩いていくのがよいでしょう。
二王座歴史の道の景色

サーラ・デ・うすきは憩いや交流を目的とした交流ホールとふれあい広場、また臼杵市の台所として食の情報発信をする飲食店が数店並ぶ複合施設です。休日の昼頃はとても混みあっています。
かつてここには臼杵藩の家老職を務めた村瀬氏の屋敷がありました。明治時代に入ると臼杵藩と取引があった鑰屋(かぎや)が買い取り醤油や味噌の醸造所を建てました。平成十二年に臼杵市が工場跡を買い取り現在の形になりました。

旧稲葉家長屋門。
臼杵藩主稲葉氏の分家の門跡です。

旧稲葉家土蔵。
長屋門と同じで稲葉氏分家の土蔵です。身分の高い武士たちが住んでいた一帯なのですね。

かつては私のような下々の人間は歩くことすら許されない場所だったのでしょう。

仁王山善正寺。
1602年(慶長7)に創建された浄土真宗本願寺派のお寺です。説明板によると美濃(岐阜)から願了法師が来たとあるので稲葉氏が臼杵に移封したとき連れて若しくは付いて来たのだと思います。
1732年(享保17)に焼失。
1744年(寛保4)に再建され現在に至ります。

竹生山善法寺。
1334年(建武1)創建の浄土真宗大谷派のお寺。
開祖の廓玄上人は佐々木義清の曾孫とされています。信州松本の正行寺で親鸞聖人の教えを学び、その後各地を巡り教えを広め臼杵に善法寺を建立しました。


旧真光寺跡に建てられた休憩所。
真光寺は前述した仁王山善正寺の支院として1716年(享保1)に建てられました。

旧片切家屋敷跡。
これは西南戦争の臼杵の戦いで戦死した片切八三郎の屋敷です。臼杵の戦いについて少しだけ↓で触れています。

旧斉藤家屋敷跡。
臼杵藩士の斉藤氏の住宅跡です。
斉藤氏は美濃(岐阜)の出身で初めは筑後の有馬氏に仕えましたが、後に稲葉氏に召抱えられました。
終わりに

二王座歴史の道には城下町の風景に溶け込んだ飲食店やお土産屋が並んでいます。
臼杵観光に臼杵城と併せておすすめ出来るスポットです。あとちょっと離れているけど国宝・臼杵石仏もいいですね。
おしまい!